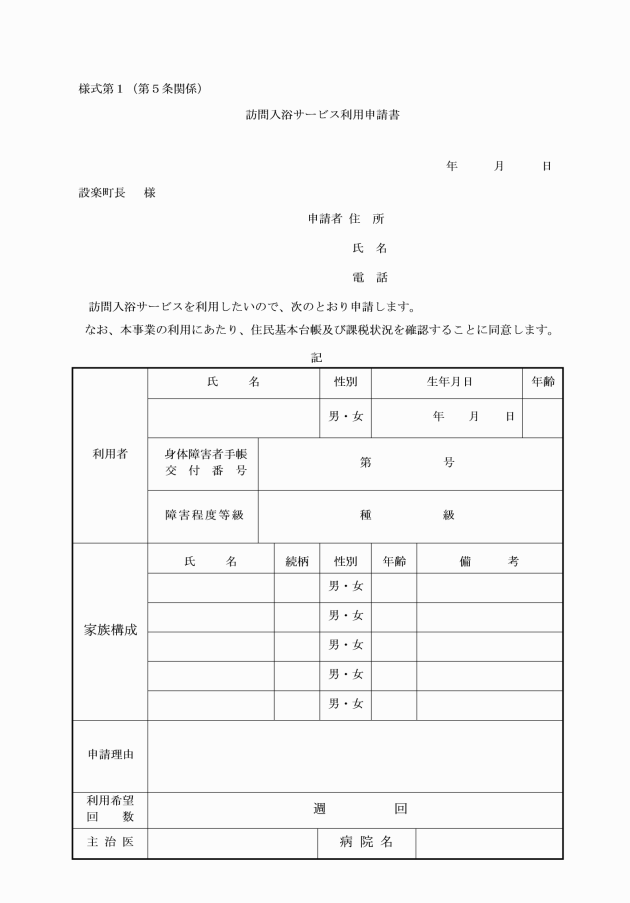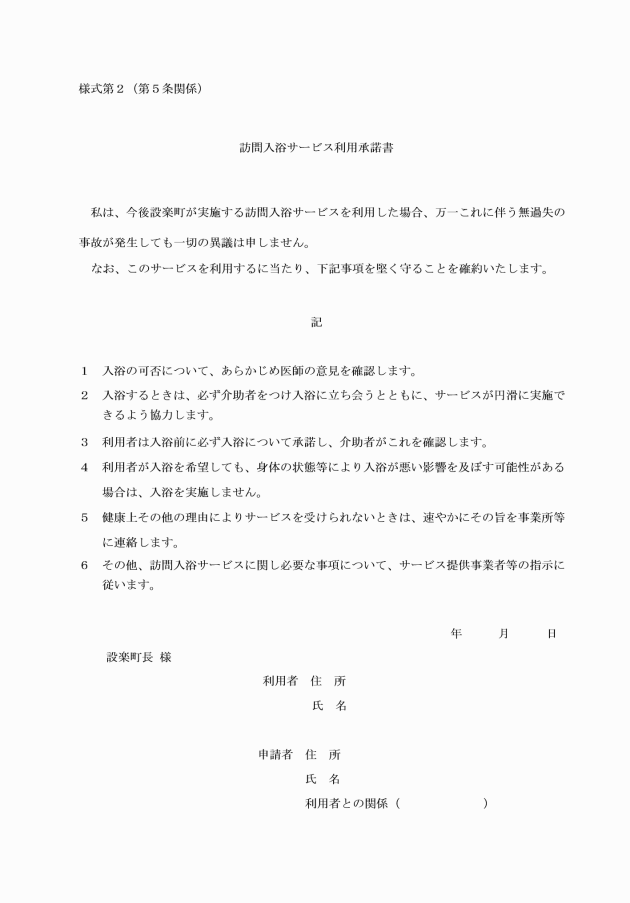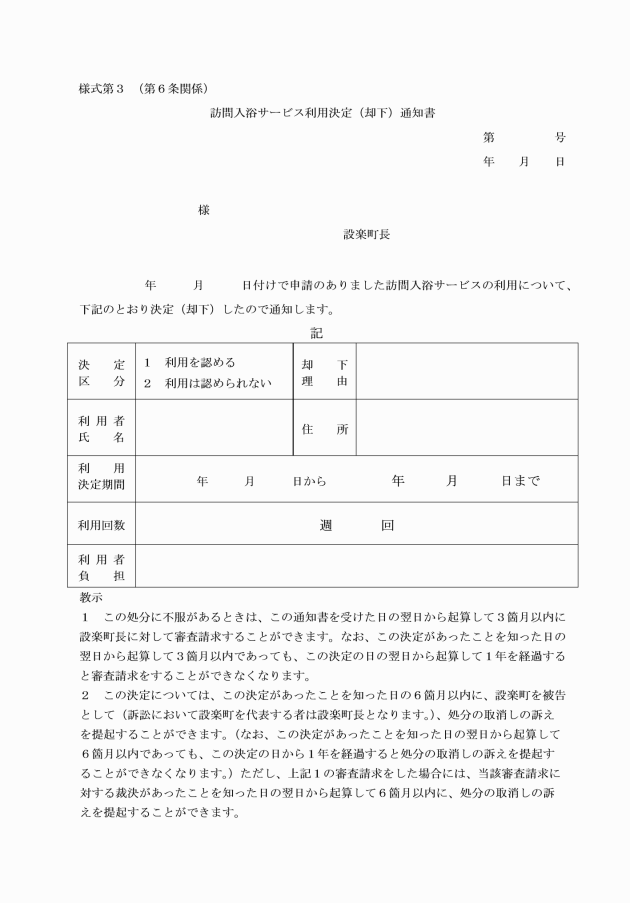○設楽町訪問入浴サービス事業実施要綱
令和6年3月28日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭において入浴することが困難な重度の身体障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、移動入浴車による入浴サービス(以下「事業」という)を行い、障害者等の健康保持とその家庭の福祉向上に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、設楽町とする。ただし、利用の可否及び費用負担の決定を除き、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住する障害者等で、次の各号のいずれにも該当する者及び町長が特に必要と認めた者とする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める肢体不自由の障害程度が1級又は2級に該当する者
(2) 医師が入浴可能と認めかつ、家庭における入浴が困難な者
(3) 病院・施設等に入所していない者
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)によるサービス対象者でない者
(事業内容)
第4条 事業の内容は、障害者等の居宅を訪問し、浴槽(障害者等の入浴に適したもの)を提供して実施する入浴及び洗髪とする。
2 事業の利用回数は、原則として1週間に2回を限度とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
3 対象者の健康上の理由により入浴又は洗髪を実施せず、清拭等を行った場合は、事業を利用したものとみなす。
(費用)
第7条 町長は、前条の決定に基づき事業を実施した受託者に対して、当該サービスに要した費用(以下「サービス費」という。)を支払うものとする。この場合において、町長が支払うサービス費の金額は、当該サービスにつき1人1回当たり、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に基づき算定した当該基準別表に定める訪問入浴介護費の金額と同額とする。
第8条 利用者は、サービス費の一割に相当する額(当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。以下「利用者負担額」という。)を受託者に負担しなければならない。
3 日常生活用具給付事業を除く地域生活支援事業及び障害福祉サービスの利用者負担額を合わせた額が、前項で規定する額を超える場合は、負担上限額を超える部分について、利用者は高額地域生活支援サービス費支給申請書を町長に提出しなければならない。
4 前項の申請書を受け付けた町長は、支給の要否の決定を行い、その旨を高額地域生活支援サービス費支給(不支給)決定通知書により速やかに申請書に通知するものとする。
第9条 受託者は、町長に対し、毎月10日までに前月分の事業の利用状況を報告するとともに、サービス費から利用者負担額を控除した額を請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、利用月の翌月の末日までに受託者に支払うものとする。
(利用の中止等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの利用を廃止し、又は停止することができる。
(1) 対象者が、第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 道路事情、災害その他特別な事情により移動入浴車を派遣できないとき。
(3) その他事業の運営に支障がある行為があったとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(設楽町老人入浴サービス事業実施要綱の廃止)
2 設楽町老人入浴サービス事業実施要綱(平成17年設楽町告示第24号)を廃止する。
別表(第8条関係)
区分 | 区分 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 対象者が18歳未満の者で、市町村民税所得割の合計が28万円未満の世帯 | 4,600円 |
対象者が18歳以上の者で、市町村民税所得割の合計が16万円未満の世帯 | 9,300円 | |
一般2 | 上記のいずれにも該当しない世帯 | 37,200円 |
備考
この表において「世帯」とは、対象者が18歳以上の場合は本人及び生計を同一にしている配偶者、18歳未満の場合は保護者の属する住民基本台帳上の世帯とする。